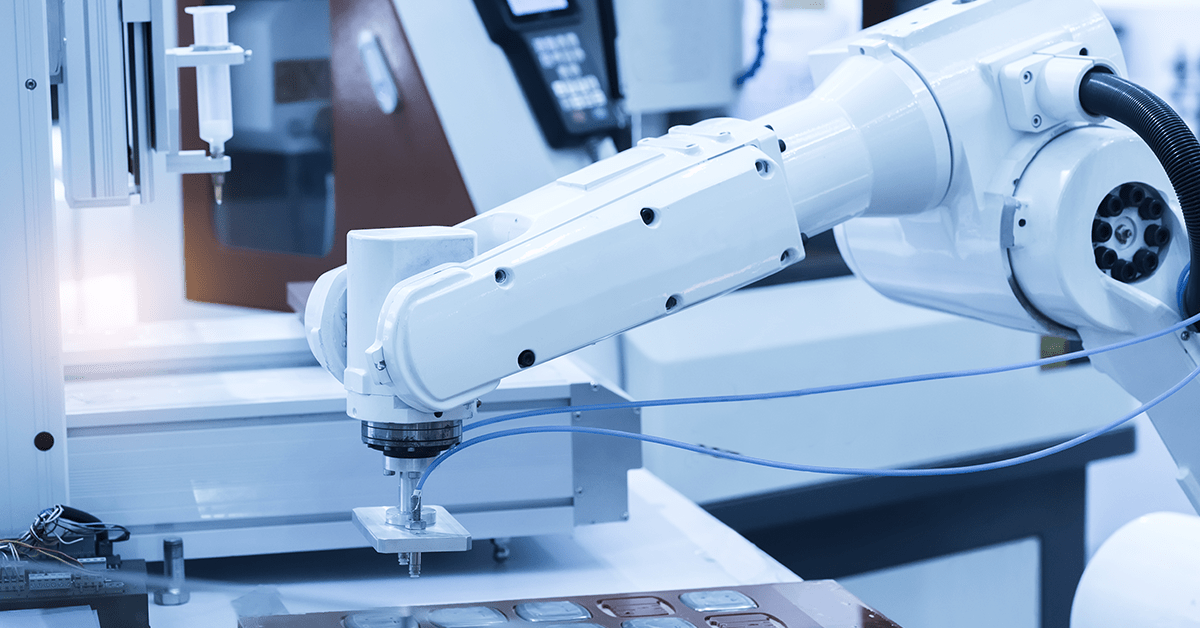クルマに搭載される半導体、ちょっと整理してみましょう。
まず大きく分けると、電気動力の供給に関わる「パワー半導体」、電子機器をコントロールする「マイコン」、車そのものの制御や通信を担う「ECU」、そして生成AI用のチップまであります。
このうち、パワー半導体を除いた演算用チップが、いわゆる“普通の半導体”。開発の方向性は大きく3つ、①回路の高密度化、②チップレット化、③インハウス化です。
① 回路の高密度化
半導体は「回路線幅」でよく比較され、数値が小さいほどコンパクト。スマホ向けはすでに5nm、一方でクルマ向けの汎用品は22nmあたりです。建設中の熊本のTSMC工場も、この22nm前後を中心に作るので自動車用途がメインなのがわかります(ちなみに、第三工場では3nm品を予定)。北海道のラピダスは2nmを目指していますし、中国の新興BEVメーカーNIOではすでに5nmチップを使い始めています。クルマ向けも間違いなく高密度化が進むでしょう。
② チップレット化
チップの機能を分散して組み合わせる設計です。SOC(システム・オン・チップ)への負荷が高まると、複雑な判断をECUに送らず末端のSOCで処理させる方向になります。そのとき汎用品をつなぎ合わせた方がコスト面でも有利。さらに基板を小型化できるので、歩留まり向上にもつながります。
③ インハウス化
BYDが電子機器・半導体・LiBを自社グループでまかなうことでBEV界をリードしているように、自動車OEM各社も半導体の内製化やパートナーシップ強化を進めています。前述のNIOの5nmチップは内製。トヨタはデンソーに電子機器開発を統括させつつ、熊本TSMCに出資。テスラはサムスン電子から4nm品の供給を受けるなど、主要プレイヤーはしっかり押さえにかかっています。
クルマの形がどう変わろうと、二次電池・モーター・半導体は必ず搭載され続けます。そして、自動運転が進めば、さらに複雑さは増すでしょう。だからこそ、この3つをどう押さえるかは、私たちサプライヤーにとって重要なのです。