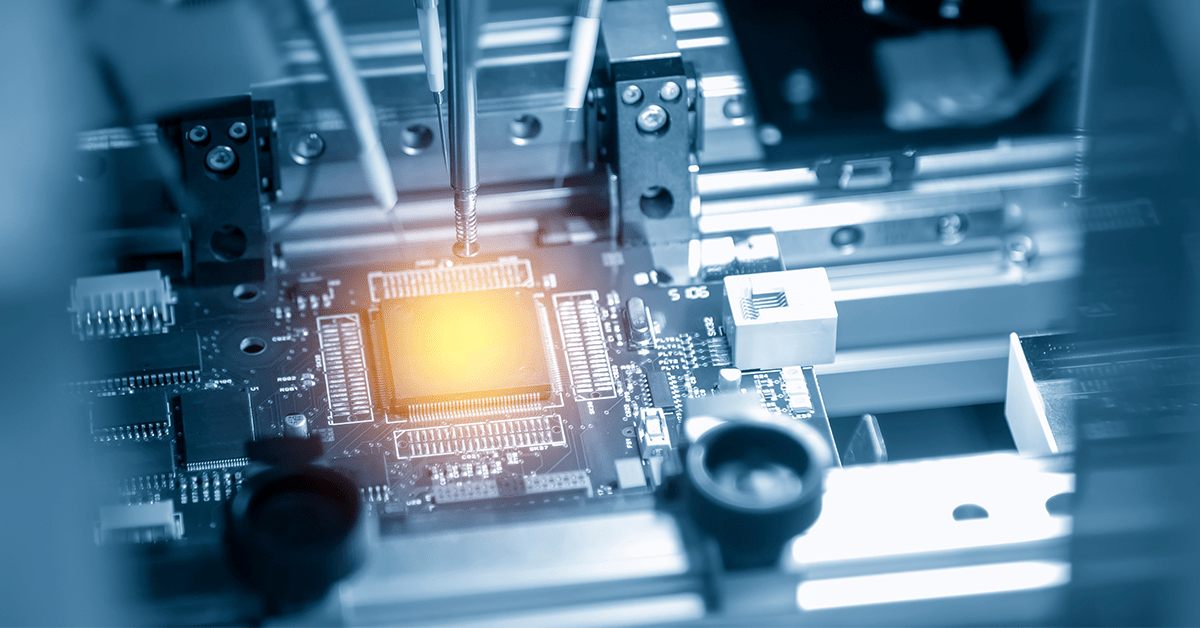生成AIが広げる未来、その裏で増える負荷
生成AIの利用は日々拡大し、サーバーへの負担も急激に増しています。電力消費は今後5年で約3倍に達するとの予測もあります。日本語に最適化したコンパクトなLLMの開発が進む一方で、自動運転などクルマ分野でも生成AIの活用が進み、データ処理の高速化が求められています。こうした状況から、機器への負荷は当面の間、減るどころかさらに高まっていくと考えられます。
クルマ向け半導体も加速する高密度化
クルマ向け半導体は、これまで安全性やコストを重視しており、スマートフォンのようなシビアな小型化は進んでいませんでした。現在も20nmクラスのものが主流ですが、中国のBEVメーカーNIOでは、自社開発による5nmピッチのスマートフォン並みにコンパクトな半導体の搭載が進んでいます。さらに、部品の有効面積を最大限に活かすため、3D基板化も進展しています。
高密度化が招く“熱”の新たな課題
回路が密になり、データ処理が高速化すると、次に立ちはだかるのが発熱対策です。こうした背景から、より耐熱安定性の高い基板用樹脂の採用が広がっています。もちろん冷却技術も進化していますが、基板だけでなくケーシングなど周辺部品の材料選定にも「熱をどう扱うか」という視点が欠かせません。
「耐える」だけでなく「熱を生まない」発想へ
従来は「何℃まで耐えられるか」が材料選定の目安でしたが、今はそれだけでは不十分です。重要なのは「熱を生まない材料」という新たな視点です。その鍵のひとつが誘電率。プラスチックを構成する分子や充填材が特定周波数で共振し、激しく動くことで自ら熱を発生させる現象が起きます。これが局所的な熱疲労の原因にもつながります。
樹脂特性を理解してこそベストな設計に
見た目には熱変形がなくても、形状的に熱が逃げにくいことで特定部位だけ熱疲労が進むといったトラブルは少なくありません。高レベルの熱マネジメントを実現するには、樹脂ごとの特性や適性を深く理解したうえでの設計が不可欠です。
プラスチックのプロがサポートします
私たちスターライトは、プラスチック製品を“トコトン面倒みる”プラスチックのプロです。材料の選び方から熱対策まで、ぜひお気軽にご相談ください。